お話「ラムネ屋トンコ」
第五十一回 昭和三十三年 秋 恥ずかしいことばかり
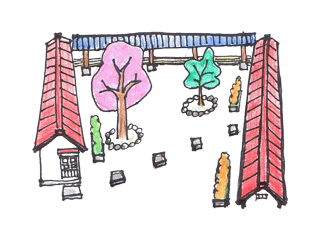
中学一年の二学期の始め頃、通学途中の道路に、きれいに輝く金の懐中時計が落ちていた。
「拾って届けたら面倒な事になるから、拾わない。」「拾って持っていたら、泥棒と間違えられたらいやだから、拾わない。」と友達。
祖父の形見の古い懐中時計を、父が大切に引き出しに締まっているのを思い出した。
持ち主の困った気持ちが伝わってきたので、そのままにして置くことができない。
私は拾って交番に届けることにしたが、授業中もポケットの中の懐中時計が気になる。
放課後大急ぎで交番に届けると、名前などを聞かれたので学年と名前だけを伝えた。
次の日「懐中時計の落とし主から、お礼にと絵の具が一箱届いた。」と担任が教室で話した。
みんなに知られてしまい、何か言われた訳ではないが、恥ずかしい。
やっぱり、拾って届けなかった方がよかった。
拾って届けても名前を言わなければよかったとも考えた。
そのことで、職員室に呼ばれて、担任に話をして絵の具を受け取っていたら、昼の休憩時間が終わりそうになった。
急いで飛び石を渡って便所に行こうとした。
長い校舎の両端に渡り廊下があるが、中程に近道用の四角いブロックが飛び石の様に置いてある。
そのブロック石を跳びながら渡っていると、足を踏み外して転び、ブロック石の角で思いっきり腰を打った。
あまりの痛さに気を失いそうになったが、「気を確かに、気を確かに。」と自分に言い聞かせて絵の具の箱をしっかり持っていた。
一瞬気を失いすぐ気が付いたが、右腰と右膝がとても痛い。
便所に行って、打った腰を見ると、凹んで赤くなっていた。
また恥ずかしいことが起こったが、みんなに言わないことにした。
家に帰る途中かなり痛いので、近くのU病院で診て貰うことにした。
「腰の骨は折れていないようだ。様子をみよう。」とU先生はニコッとして、シップをはってくれ、膝の擦り傷も治療してくれた。
中学生になっても転んだのかと、先生が思っているように感じ、恥かしくなる。
次の日も、歩きにくいしとても痛い。
誰かが、ブロックの所で転んだら危ないので、担任に報告したくなったので、職員室に行った。
「中庭のブロックの飛び石は離れすぎていて、跳んで渡っていると足を踏み外して転び、怪我をして痛い思いをしました。」「ブロックの角が尖っていて危ないので、ブロックの数を増やして近くに置いたら危なくないのでは。」と担任に提案までした。
「今まで、飛び石で怪我をしたと聞いたことはない。」と周りの教師も笑っている。
足を踏み外して転んだのは、私だけだと気がついた。
転んだことも、ブロックを多く置くように提案したのも、とても恥ずかしい気がして、あわてて教室に戻ろうとした。
職員室に来た時と同じように、遠回りになるが渡り廊下をゆっくり歩いて教室に帰る。
途中で、父母が親しくしている家の息子のトオル君の周りに人が集まっているのが目に入った。
窓の開け閉め用の取っ手の穴に、人差し指を突っ込んで取り出せなくて青い顔して困った様子だ。
家族でお花見に行ったことがあるが、トオル君と話したことはなかった。
指を出そうと動かすので、赤く膨れてますます出にくそうだ。
こういうことは経験済みの私に任せてという気分で、「そのまま動かさないで待っていて。石鹸を持ってくるから。」と伝えた。
私は洗面所の石鹸を両手につけて、トオル君の穴の中の指に石鹸を塗り付けた。
次に、その指を押し出しながら、手首を引っ張ると、するりっと指が出てきた。
みんなは歓声を上げて拍手をした後、トオル君と私の顔を見て、なにやらヒソヒソと話している。
トオル君の指の赤みはすぐ取れたが、代わりに顔が真っ赤になって恥かしそうだ。
私まで恥ずかしくなって、頬が熱くなるのを感じる。
また、恥ずかしいことをしてしまったと気になる。
次の日の「古文」の授業中、聖君が机の下の膝の上に文庫本を置いていた。
その日の教師の気分はよくないようで、まさに低気圧だ。
「立ちなさい。今、何を読んでいたのだ。」と教師が厳しい声で、聖君に尋ねた。
彼は返事をしなかった。
「返事をしないと、授業が進められない。早く応えろ。」と教師。
彼は、冷静な顔をしたまま立っていた。
怒った顔の教師は、「返事が出来ないのなら、教室から出て行け。」と叫んだ。
聖君は表情を変えず、後の出入り口から出て行った。
教室の窓から、中庭にしゃがんだ彼の姿が見えた。
「聖君は、膝の上に文庫本を置いていて読んでいたかどうか分かりません。読んでいたとしても、みんなに迷惑をかけていません。教室から追い出す事はないと思います。」と発言したくなった。
しかし、一学期の英語のテストの時間、先生のミスを指摘した時のことを思い出した。
机の下で、手を叩いてニコッとした人もいた。
そうでない人もいて、気になった。
先生の機嫌が悪くなることをわざわざ言わなくてもいいのに、という表情だったことが後で分かった。
先生を恥ずかしい目に合わせようとしたが、そのようにならず、ミスを指摘した私自身が恥ずかしくなったのだ。
そのことを思い出し、ここで私が発言したら、先生の気分がもっと悪くなり、教室の雰囲気も悪くなるだろう。
私は様子を見ることにして、発言しなかった。
授業が終わり、教師が出て行くと、級友が聖君を呼びに行った。
彼は涼しい顔をして教室に入って席に着き、何もなかったように次の授業を受けた。
もし、私が発言したら、聖君も気分が悪くなり、私もまた恥ずかしいことになっただろう。
発言しなくてよかったと、胸を撫で下ろした。
その後も、このことが身に付けばよかったのですが。
